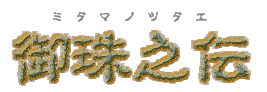第六話「記憶の瑕疵 」
夏が終わると、日暮れはやたら早くなる。
部活を終えた生徒達が外に出てみると、日は既に沈み、西の空に赤い
「あ〜あ、腹減ったなぁ」
「コンビニでアイス食べて帰ろ、アイス」
「新発売のおにぎりがさぁ」
校門を出た部員達は、にぎやかにおしゃべりをしながら、三々五々に帰っていく。
部活が遅くまであった日は、家の近い者同士、男女一緒になって帰宅するのが
「すみません、遠回りなのに」
紅子が口ではそう言いながら、心中では、チャンス到来とほくそ笑んでいたことは言うまでもない。
自分が消えれば、親友は憧れの君と二人きりではないか。
そんな彼女のもくろみなど露とも知らない藤臣は、
「かまわないよ」
と、普段通りののんびりした笑顔。
春香はと見ると、気のせいだろうか、なんだか少し元気がなかったが。
ともかく、自分たち三人だけになったら、行動開始だ。
「あの。あたし、ここで失礼します」
紅子が声をかけると、藤臣と春香は、ほぼ同時に彼女のほうを振り向いた。
「父から買い物頼まれてるので、あのスーパーに寄らないと」
と、横断歩道の向こう側にあるを指さす。
信号はちょうど、赤から青に変わったところだ。まるで図ったような、いいタイミング。
しかし、藤臣はいきなり別行動を取ると言い出した後輩に当惑した様子で、
「それなら、僕たちも」
一緒に、と言いかける。
が、その言葉を、紅子は素速くさえぎった。
「いえ、ちょっと時間かかるかもなので、先に帰っちゃってください。それじゃ」
早口で言うと、点滅を始めた青信号に急かされたふりをして、駆け足で横断歩道を渡ってしまった。
すれ違いざま、春香の耳元に「ガンバレ」とささやくことを忘れずに。
流れ出した車の群れの向こうで会釈する紅子に手を振りながら、藤臣はどことなく釈然としない面もちで、
「忙しいヤツだなぁ」
などとつぶやいていたが、春香は親友が気を利かせてくれたのが、嬉しくて仕方なかった。
ありがとう、紅子!このお礼は必ずするからね!!
「やっぱり、追いかけていったほうがよくないかな?」
藤臣が心配そうに言った。
「仮にも女の子なんだし、何かあったら……」
「大丈夫ですよぉ」
春香は笑って言った。
「紅子の家って、武術道場なんです。たいていの痴漢やチンピラなんか、敵じゃないって感じ」
藤臣は目を丸くした。
「そ、そんなに強いのか、一色って?」
「見えないでしょー?でも、中学の頃なんか、すごかったんですよっ。他校の不良さんグループから引き合いが来たりして」
二人は春香の家に向かって歩きながら、話を続けた。
「
「幼稚園からずっと一緒です。家も近いし、ま、いわゆる腐れ縁てやつかなァ」
藤臣は、声を立てて笑った。
「腐れ縁て」
「だって、ほんとにずーっと一緒なんですよぅ?紅子のことなら、たいていのことは知ってます」
「へーぇ」
藤臣は感心したように相づちを打った後、ふと冗談めかした口調で、こう言った。
「それじゃあ、松居に訊けば、一色に今好きな人がいるかどうかもわかるのかなぁ……」
腕時計を見ると、午後六時半。三十分以上、店内で過ごしたことになる。
さすがにもう藤臣たちと鉢合わせることもないだろう。
そう思い、紅子はスーパーを出た。
父親から頼まれた買い物がある、というのはうそではない。
ただ、別に急ぎの物ではなかったというだけだ。
しかし、今日このときにこの口実を利用しなくていつするというのか。
それにしても、レジ袋が重い。
時間稼ぎをかねて食品売り場へ行き、冷蔵庫で残り少なくなっていた物まで買ってしまったので、通学鞄に加えて、けっこうな荷物になってしまった。
春香はうまくやっただろうか。
いきなり告白というのは無理でも、何かちょっとした進展があれば、ひと肌脱いだかいもあるというものだ。
そんなことを考えながら自宅の門をくぐると、玄関前に誰か立っているのが見えた。
「おかえり」
玄関前の人影が言う。
「遅かったな」
その声と、玄関の引き戸ごしにもれる明かりで、紅子はその人影が自分の父親、
今年で四十歳になる彼は、身長こそそれほど高くないが、武術家らしい、がっしりした体格の持ち主である。
紅子は「ただいま」と言った後、
「部活のあと、買い物してたから」
と、スーパーのロゴ入りレジ袋をちょっと持ち上げて見せた。
「それより父さん、こんなとこで何してんの?」
「客が来るんでな。出迎えだ」
少しばかり不機嫌そうに答える父親は、いつもと同じ和服姿だ。
が、薄明かりに見えるそれは普段用のものではなく、上等の
客人というのはよほど大事な人物らしい。誰だろう?
「お客さんて、今から?こんな時間に?」
紅子は玄関を開けて上がりかまちに重い荷物を降ろし、まだ外にいる父親を振り返って尋ねた。
すると、
「ああ」
ますます不機嫌そうな玄蔵の声。
だが紅子は頓着せずに戸口まで戻り、続けた。
「ねー、そのお客さんってさ、今朝早く、電話してきた人?たしか、
朝の七時すぎ、若い男の声で電話があったのを、何となく思い出しながら言う。
玄蔵が子機を持って自分の部屋へ行ってしまったので、話の中身はわからない。
ただ、電話に出る父の顔が、今と同じに暗かったのが印象に残っている。
紅子としては、心配しているつもりで訊いたのだが、玄蔵は好奇心ゆえの発言と思ったらしい。
「お前には関係ない」
彼は怒ったような口調で娘の言葉を一蹴すると、
「さっさと家に入って、メシでも食ってろ」
ぴしゃり、と紅子の鼻先で戸を閉めてしまったのだった。
「なに、あれ!むっかつく!」
紅子は買ってきた食料品を乱雑に冷蔵庫につっこんだあと、どかどかとわざと大きな音を立てて階段を上り、二階にある自室へ向かった。
思い切り大きな音を立ててドアを閉め、ベッドに
「虫の居所が悪いか何か知らないけど、娘に当たるなってのよね!」
などと大声で独りごちては、かなり乱暴な動作で彼女は制服から私服に着替えた。
室内は一応、ぬいぐるみやピンク・花柄系のカバー類で女の子らしく飾られているが、本棚に武術関連の本が並んでいたり、クローゼットに
本棚には他に、アンティークな
古いほうは、赤ん坊の頃の紅子とその両親を撮ったもの。
彼女の母親は、これを撮影した翌年、亡くなっている。元々病弱で、紅子を産んでからは特に具合が良くなかったらしい。
以来、母親代わりになって紅子を育ててくれたのが祖母。
すなわち、新しいほうの写真に写っている老婦人だが、彼女も去年の冬、流感をこじらせたのがもとで、あっけなく他界してしまっていた。
紅子は祖母の写真を眺めて、ため息をついた。
おばあちゃんが生きてたらなぁ……。
玄蔵はどちらかといえば紅子に甘いほうだったが、昔から時折、よくわからない理由で機嫌が悪くなることがあった。
祖母はそんなとき、
「
と、言っていた。
日奈というのは紅子の母親の名前である。
紅子は先刻の父親の様子を思い出してみた。
が、どうも死んだ妻の
どちらかといえば、何かを警戒しているような、そんな印象だった。
そういえば、と、紅子は思う。
自分が小さかった頃、何やらただならない雰囲気で、祖母と玄蔵がひそひそと話し合っていたことがあった。
あれは、いつだったろう。
あれは、たしか――小学校の――
と、そこまで考えた、そのとき。
「痛っ……?」
軽い頭痛が、紅子を襲った。
ほんの数秒、意識が痛みに集中し、彼女の思考は停止する。
そして。
「あ……あれ?」
頭痛が引いたとき、紅子は当惑の声を上げた。
「あたし……何考えてたんだっけ……?」
何か、大事なことを思い出しかけた気がしたのに。
記憶は、つかみかけたその手をするりと逃れて、どこかへ消えてしまっていた。
影も形もなく。
2009.10.18改筆
このページの文書については、無断転載をご遠慮下さい。